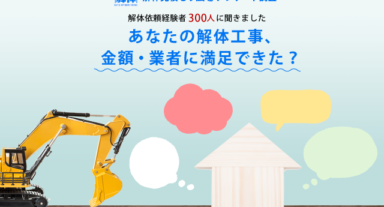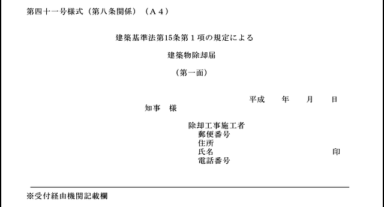建物を解体すると固定資産税など税金が高くなる?解体にまつわる税務の注意点

- この記事の目次
「建物を解体すると税金が上がる」という話を聞いたことがありますか?人によっては「固定資産税が6倍になる」という噂を聞いたことがある人もいるかもしれません。しかしそれは本当なのでしょうか。
今回の記事では建物を解体した場合の固定資産税について、受けられる税額控除や、解体工事を行う際の税務上の注意点について解説していきます。
なぜ建物を解体すると税金が上がるのか
家屋の劣化が進みいよいよ解体を、と検討している方にとっても税金が高くなるかもしれないということは気になることです。まず、「建物を解体すると税金が上がる」というのはどういうことなのでしょうか。
ここで言う税金とは具体的に「固定資産税・都市計画税」のことを指しています。では建物の解体が固定資産税・都市計画税にどのような影響を与えるのでしょうか。
住宅地用地では固定資産税の特例措置が受けられていた
この家屋を解体すると税金が高くなるという背景には、そもそも住宅が建っている土地の場合、土地にかかる固定資産税が軽減されていたという事実があります。
つまり家屋を解体することで、これまで既に受けていた固定資産税の特例措置が受けられなくなり、税額が高くなるのです。
住宅用地は1/6の軽減特例を受けていた
よく建物を解体すると「固定資産税が6倍になる」という話を耳にすることがありますが、これは、「対象の土地に建物がある場合、固定資産税が1/6になる」という軽減特例を受けていたということがその背景にあります。
建物がある場合の固定資産税の軽減割合
建物がある場合、具体的にどのような軽減措置を受けているのでしょうか。
| 固定資産税 | 都市計画税 | |
|---|---|---|
| 200㎡以下 | 固定資産税評価額の1/6 | 固定資産税評価額の1/3 |
| 200㎡を超える部分 | 固定資産税評価額の1/3 | 固定資産税評価額の2/3 |
住宅用地で200㎡以下の部分について、建物がある場合には固定資産税は固定資産税評価額に1/6をかけることができ、都市計画税は固定資産税評価額に1/3をかけることができます。
200㎡を超える部分についての固定資産税は固定資産税評価額に1/3、都市計画税は固定資産税評価額に2/3をかけることができます。
例えば200㎡で7,000万円の土地があった場合、固定資産税、都市計画税は以下のように計算されます。
7,000万円×1/6×1.4%=約16.3万円(固定資産税)
7,000万円×1/3×0.3%=約7万円(都市計画税)
16.3+7=23.3万円(固定資産税+都市計画税)
この場合、固定資産税と都市計画税の負担はおおよそ23.3万円となりました。
実際は解体により税金が6倍になるわけではない
ただし注意しなければいけないのは、固定資産税の特例が受けられなくなるからといって税金がそのまま6倍になるというわけではありません。
国は「負担調整措置」という税金が緩やかに上がっていくような措置を用意しているため、実際に解体を行った後でも税金負担は3倍から4倍程度に上がるというのが現実的です。
負担調整措置とは
この負担調整措置は平成6年の評価替え当時に導入された制度で、土地の固定資産税・都市計画税の評価額水準が地価公示価格の7割程度に統一され、急激に上昇したことに伴い税負担をゆるやかに上昇させることとして決められた制度的緩和措置です。
ただし、平成24年度税制改正によって住宅用地の負担調整措置について段階的に、据置特例が縮小・廃止されることとなっています。
解体により家屋の固定資産税はなくなる
また、住宅を取り壊すことによって特例措置はなくなりますが、家屋が無くなるため家屋部分の固定資産税は発生しません。
つまり、建物を解体することで土地についての軽減措置は受けられなくなり土地部分は税額が高くなりますが、解体した建物の固定資産税と都市計画税はかからなくなるのです。
そのことから、土地の評価額が低い場合などは建物を解体することによって税額が低くなる可能性もあります。
ただし、都心部に古い家などの場合には、建物の固定資産評価額は少なく土地は都心部であるため高く評価されているため、総合的に固定資産税は上がることが考えられます。
いつ時点の固定資産で評価されるのか
では固定資産税はいつ時点の資産として評価されるのでしょうか。固定資産税の課税判断は、毎年1月1日時点で行われます。その年の1月1日に家屋が建っていれば、その後年の途中で家屋が取り壊されても1月1日時点の評価によって計算されるのです。
よく建物の取り壊し後、すでに支払っている固定資産税の建物部分について、もう建物はなくなっているため還付を受けられるとお考えの方もいますが、取り壊しによる固定資産税の還付などは特に発生しません。
解体によって発生するそのほかの費用
解体によって発生するのは固定資産税・都市計画税などの税金のほか「滅失登記費用」が発生します。
建物滅失登記は建物を解体してから1ヶ月以内に建物の所在地を管轄する法務局に建物滅失登記申請書を提出しなければなりません。手続き自体に費用はかかりませんが、事前に建物の登記情報を調べる必要があるため、登記簿謄本の取得費用が発生します。
費用は登記簿謄本1通につき1000円前後かかります。またそれらの手続きを専門家に依頼する場合、代行費用はおおよそ4万円前後となります。
更地を相続した場合と建物が立っている場合の相続税
建物の解体により固定資産税・都市計画税の他に影響があるのは「相続税」です。土地を相続する場合、更地であるのと建物が立っているのとでは相続税の評価額が大きく異なり、相続税の負担額も変わってきます。
アパート・賃貸物件を建てることで評価額を抑えられる
例えば更地に賃貸物件を建てると、その土地は貸家建付け地となり土地の評価額は最大で20%下がります。また建物部分に関しても、アパートなどの賃貸建物を建てることにより建物費総額の50%前後に相当する金額の相続税評価額を下げることができます。
さらに相続では貸家などの賃貸建物については借家人がいることにより所有者の利用が制限されますので、その建物の固定資産税評価額から借家権相当額、つまり30%を控除した金額がその建物の評価額となります。つまり評価額を3割減させることもできるのです。
特定空き家と判断された場合の税金について
これまでの話から、建物は解体せずにそのまま持っておいた方が良いとお考えの方もいるかと思います。しかし、解体をせずに建物が建っていたとしても軽減措置を受けられなくなる場合もあるので注意しましょう。
平成26年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が立法化されました。この措置によると、
- 空き家が放置され著しく保安上危険となる恐れのある状態
- 衛生上有害となる恐れのある状態
- 景観を損なっている状態
- 周辺の生活環境の保全が損なわれる状態
にあてはまると、「特定空き家」に認定され、固定資産税の減額措置の適用対象から外れてしまいます。
特定空き家に認定されると固定資産税の軽減特例が受けられない
つまり土地の上に家屋があったとしても、あまりにも危険な状態である場合や周りに迷惑がかかるような状態の建物である場合、固定資産税の軽減特例が受けられないということです。
そのような状態の建物である場合、建物が建っていたとしても減額措置は受けられませんので解体を検討しても良いでしょう。また市区町村によっては、除去費用の一部(解体費用の1/2〜1/5程度)を補助する制度がありますので確認しましょう。
解体後の税金対策
建物を解体したあと、更地として保有していると高額な固定資産税が毎年発生し続けます。ここではどのようにしたら解体後の税金を抑えることができるのか、いくつかの対策をご紹介します。
公益のための固定資産とする
更地の状態でその後何も利用する予定がないような場合、一定の用途に使用される土地については非課税になる特例があります。
この制度では、例えば東京都23区内では「公益のために直接専用する固定資産」については申請することにより固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。
公益のための固定資産とは具体的に、
- 町会事務所
- 遊び場
- 公共用歩廊等(償却資産)
- 土地区画整理事業による仮換地のうち減歩された部分
- 開放型病院等
- 幼稚園
- 専修学校及び高等課程専修学校
- 各種学校
- 学生寄宿舎
- 社会福祉施設付属宿舎
- 看護師養成施設及びその学生寄宿舎
- 非課税となる病院付属の看護師寄宿舎
- 特定保存樹林地
- 認証保育所
- 地域のケア付き住まい
- 民設公園用地
などが該当します。特に用途がない更地であれば、このような方法で税金を抑えることを検討しましょう。
解体のタイミングを検討する
先程ご紹介したように、固定資産税の額は1月1日時点の状態によって決まります。つまり解体の時期を調整することによって税金を抑えられます。
仮に解体後税金が高くなるという場合であれば時期を1月1日よりも遅らせることで固定資産税を抑えられます。逆に解体により固定資産税が下がるという場合であれば、1月1日よりも前に行うことでこちらも固定資産税を抑えられます。
固定資産税を少しでも抑えたいと言う場合には解体の時期を検討しましょう。
解体後に土地を売却する
特に利用していない土地であれば保有して固定資産税を払い続けるよりも、売却してしまった方が良い場合もあります。
ただし、土地を売却することで固定資産税は発生しなくなりますが、建物を解体して売却する場合は利益が出ると譲渡所得とみなされ所得税がかかります。
この譲渡所得の計算は、収入金額から必要経費を差し引き、そこから特別控除額を引いて算出します。
収入金額-必要経費(取得費+譲渡費用)-特別控除額
土地売却による所得税
この計算式により、プラスとなる場合には所得税が発生となります。所得税は短期譲渡か長期譲渡かによって税率は異なり、短期譲渡(所有期間5年以下)に該当する場合には30.63%、長期譲渡(所有期間5年超)に該当する場合には15.315%の税率となります。この所有期間というのは、売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかの判断となります。
所得税は申告納付となっており、資産を譲渡した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに申告します。納付方法は申告期間中に税務署か金融機関で納付、または振替手続きを行うことで4月20日前後に指定口座から引き落とし納付にも対応しています。
土地売却による住民税
そして忘れてはいけないのが、この譲渡所得に対して住民税も発生するということです。住民税の税率も短期譲渡か長期譲渡かによって異なり、短期譲渡の場合9%、長期譲渡の場合5%となります。
住民税は申告した年の翌年、6月から8月、10月、さらにその翌年の1月と4期に分けての納付となります。こちらの住民税の納付は時期がずれていますので注意が必要です。
解体費用を譲渡所得計算の必要経費に算入するためには
譲渡所得を算出するための計算式の「必要経費」部分に建物の解体費用を入れることができれば、所得税を大幅に抑えられます。
解体費用は一定の場合必要経費に入れることはできますが、必要経費として認められるには物件の譲渡のために必要となった経費であることが条件となります。つまり売却のために建物の取り壊しが不可欠、というような場合には解体費用も必要経費とすることができるのです。
譲渡の予定が特にないのに売主の都合で建物を解体した場合、解体費用を必要経費に含めることはできませんので気をつけましょう。
解体後にもマイホーム譲渡の控除特例が受けられる
マイホームを売った時には、譲渡所得から最大3000万円まで控除できるという特例があります。この特例は原則、家屋の所有者がマイホームを譲渡した時に受けられるものです。
家屋を取り壊して敷地を売った場合には原則この特例は受けられませんが、次の要件にすべて当てはまる場合、この3000万円の特別控除の特例を受けることができます。
- 家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る契約をしていること。
- その家屋に住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
- その家屋を取り壊してから、その敷地を売る契約をした日まで、貸付けその他の用に使用していないこと。
ただし、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに、残った家屋が居住できる状態になっている場合にはこの特例は受けられません。
この3000万円の特別控除の特例は受けることができれば、譲渡所得税や住民税を大幅に抑えられますので、解体後に土地の売却をお考えの方は要件に該当するかどうか検討してみましょう。
まとめ
今回は解体にまつわる税務・税金対策などについて解説しました。保有していた建物を解体すると、これまで受けていた固定資産税の軽減特例が受けられなくなり、土地に対する税額が上がってしまいます。
ただし、必ずしも固定資産税が6倍に上がるというわけではなく、「負担調整措置」があるため税額負担の上昇は緩やかです。また建物部分についての固定資産税はなくなるため、土地部分、建物部分トータルの税金で負担が増えるかどうかを判断しましょう。
解体後、更地となった土地を特に利用する予定がなければ公共施設として無償で貸与することなどにより固定資産税の減免を受けることができます。
また売却をお考えの方は、譲渡所得に対し3000万円の特別控除の特例を受けることもできる場合もあるので用件を確認してみましょう。その他解体のタイミングなどによっても税金負担が異なる場合がありますので、具体的な内容は専門家に相談しながら進めていくことをおすすめします。
関連リンク:相続税相談広場
 解体見積もり広場
解体見積もり広場