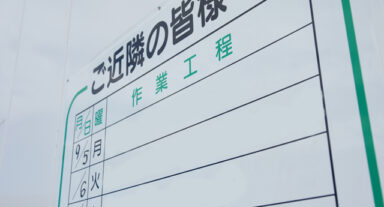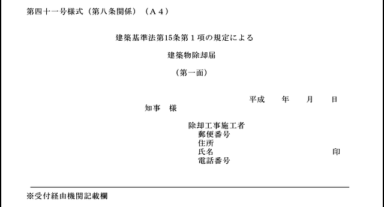解体工事の見積書でチェックすべき項目と良し悪しの見分け方を解説

解体工事を依頼する際に、見積もりの内訳や作成方法について疑問に感じるという方もいるのではないでしょうか。今回は、解体工事の見積書で良し悪しを見分けるコツやチェックすべき項目などについて解説します。具体的に、見積書の主な内訳なども細かく取り上げていきますので、どうぞ参考にしてください。
良い見積書と悪い見積書の見分け方
解体工事を依頼する際は解体業者に見積もり提示を依頼することになりますが、その見積もりにもさまざまな書式や提示方法があります。
良い見積書とは?
良い見積書とは、費用の詳細が細かく記載されていることです。仮設工事費や解体工事費、廃材運搬費や設備撤去費など、どの費目や作業に対してどれくらいの金額がかかるのか記載されている見積書は良い見積もりです。
さらに良い見積もりになってくると、見積書だけではなく「工事内容説明」や「サービス一覧」といった記載がある書類も渡してくれます。ここまで来るとかなり丁寧な業者であり、施主としても安心して工事を依頼できます。
悪い見積書とは?
良い見積書もあれば悪い見積書もあるのが現実です。具体的に悪い見積もりとは、工事内容の詳細や費目ごとの金額が提示されていない見積書のことを指します。
例えば、「解体工事 一式○○万円」、「解体工事 40坪 ○○万円」など、単純な金額表示だけで終わっている見積書は悪い見積もりです。
こうした表記では、どの作業や項目に対してどれくらいの費用がかかるのか把握できません。例えば、残置物の撤去費用や外構の撤去費用が含まれているのかどうか知ることもできません。
そうなると、後から高額な追加費用を請求される可能性もあり、施主としても負担が増えることになります。費用の詳細が細かく記載されている良い見積もりと比較して、トータルの金額が同じだったとしても内容がよくわからなければ不安に思う気持ちも高まってしまいます。
こうした業者には安心して工事を依頼することができないでしょう。悪い見積もりを提示してくる業者に対して、無理して契約を結ぶ必要はありません。
解体工事の見積書の主な内訳
解体工事の見積もりを依頼すると、多くのケースでは解体業者から見積書を受け取ることになります。その際に、確認したいのが内訳ごとの費用です。
中には「一式○○万円」などと記載をして見積もり提示をしてくる業者もありますが、それでは親切とは言えません。内訳ごとにいくらぐらいの金額がかかるのか提示してくれる業者の方が安心感があります。その基本となる主な内訳について理解を深めていきましょう。
仮設工事費
仮設工事費とは、解体工事に入る前に必要となる費用のことで、事前準備にかかる費用と考えておけば問題ありません。
解体工事を行う際は、作業員の安全性を確保するために足場を設置することが一般的です。また、工事中に粉じんの飛散を防止するために養生シートを設置することもあります。騒音対策のための防音シートの設置も一般的です。
こうした足場の設置や養生の設置などは、仮設工事費に含まれます。また、搬入路が狭いケースや舗装されていないケース、舗装のひび割れ防止を念頭に置いた手段として、「敷鉄板」を設置することもあります。地盤の悪い工事用通路にも設置することがありますが、敷鉄板の設置に関しても仮設工事費に含まれます。
主に仮設工事費に含まれるものをまとめると、以下の通りです。
- 足場の設置
- 養生シートの設置
- 防音シートの設置
- 敷鉄板の設置
仮設工事については解体工事に際して必要な準備であり、工事が終わったら撤去することが特徴です。敷鉄板についても工事が完了したら撤去します。こうした事前準備にかかるのが仮設工事費です。
解体工事費
解体工事の準備となる仮設工事を終えることができたら、メインの建物を壊す解体工事へと移行します。解体工事は重機などの機械を使って作業をすることが多いですが、内部解体と外部解体に分かれています。
内部解体に関しては、建物内部の造作物や残置物を撤去する作業となり、主に手作業が中心となります。そのため人件費もかかりやすく、ある程度の時間をかけて撤去することも少なくありません。
内部解体を終えたら外部解体に移ります。外部解体については、躯体そのものを重機を使って取り壊していく作業のことを指します。躯体を取り壊すことができたら、基礎部分の撤去を行います。場合によっては基礎を残しておくこともありますが、多くのケースでは基礎の撤去も含めて解体工事費に含まれます。
主に解体工事費に含まれる作業に関しては、以下の通りです。
- 内部解体
- 外部解体
- 基礎の撤去
上記の作業にかかる人件費や機材費、日数などを考慮して、総合的に解体工事費が算出されることになります。
廃材運搬費
廃材運搬費に関しては、解体工事を通して出た建築材料や産業廃棄物を所定の処分場まで運搬する際にかかる費用を指します。
解体工事をすると、コンクリートのガラや木くず、金属片やプラスチック類、紙くずやガレキなど、さまざまな廃棄物が出てきます。かつては、それらを一緒に処理しても問題ありませんでしたが、現在では品目ごとに分別して処理を行う分別解体が義務化されています。
分別解体
解体工事で出る建設資材の廃棄物を種類ごとに細かく分別し、計画的に工事を進めながらリサイクルすることを念頭に置いた規定。建設リサイクル法に基づいて制定。
そのため、廃材を運搬する際も廃棄物の品目ごとに分けて運搬を行う必要があります。施主としてもその点を念頭に置いて、正しく分別が行われているか確認することが大切です。運搬を行うのは、廃材運搬専用のダンプトラックです。通常のダンプより荷台が高くなっているところが特徴で、廃棄物処理場に向けて運搬を行います。
ダンプにかかる費用や運搬費用、人件費などを合算して廃材運搬費が算出されます。
廃材処分費
廃材運搬費とは別に、廃材を処分するためにかかるのが廃材処分費です。分別解体の考え方にも触れましたが、廃材や産業廃棄物に関しては適当に処分してはいけません。
特に分別もせず、森林や地中など、適当な場所に捨ててしまうと不法投棄の扱いとなり、解体業者などが罰則を受けることになります。そうならないようにするため、許可を持っている指定の産業廃棄物処分場で適切に処理することが求められます。
廃材処分費も解体費用の内訳に含まれており、その負担も施主が行うことになります。不法投棄は法律的にもモラル的にも悪い行為なので、絶対にしないことが大切です。
設備撤去費
設備撤去費とは、ライフラインの撤去費用のことを指します。具体的には、以下のようなライフラインの撤去にかかる費用です。
- 電気
- 電話
- ガス
- 水道
- インターネット
設備撤去は施主自身で各関係会社に連絡を入れて行うことも多く、その場合は解体費用には含まれません。電気は地元の電力会社に依頼すれば、多くのケースで無償で撤去してくれます。また、電話に関してもNTTに連絡を入れることで撤去してもらえます。
ガスや水道に関しては、解体工事との兼ね合いで設備撤去を誰が行うのか話し合いを行う必要があります。いずれにしても、安全な形で撤去することが重要であり、そのために必要な費用がかかると認識しておきましょう。
外構撤去費
解体費用の主な内訳として、外構撤去費が含まれることもあります。外構撤去費とは、建物や家屋の本体以外の解体や撤去にかかる費用のことです。例えば、以下のような作業が該当します。
- ブロック塀の撤去
- カーポートの撤去
- 庭木の撤去
- 庭石の撤去 etc…
外構と呼ばれるものがなければ特に費用負担は発生しません。反対に、カーポートやブロック塀、庭木などがある場合は外構撤去費として費用がかかることになります。ご自身の自宅の周囲に撤去が必要なものはないか、事前に確認しておくことが大切です。
会社経費
会社経費に関しては、利益的な要素が含まれているケースが多く、特に何の費用と決まっているわけではありません。営業経費として形上されることもあります。
また、重機や機材などをリースしている場合は、リース代金も会社経費として計算することがあります。その他、作業用車両の駐車代や隣家への敷地使用料などが含まれることもあります。
その他諸々の部分を合算して、最終的な会社経費が決まります。その負担は施主が行うことになり、解体費用の総額に追加されることになります。
その他の付帯工事費
その他の付帯工事費としては、以下のような項目となります。
- 残置物撤去運搬処分
- 土間コンクリート撤去処分
- 太陽光パネル撤去処分
- テラス撤去処分
- 浄化槽撤去処分
- 杭撤去
- 井戸埋め戻し
- アスベスト除去
- 門扉撤去処分
- 物置撤去処分
- ウッドデッキ撤去処分 etc…
このように、建物本体とは別に解体や撤去が必要な項目に関して、その他の付帯工事費として請求されることになります。場合によっては、ブロック塀の撤去や庭木の撤去などの外構撤去費もまとめて請求されることがあります。
一軒家などで、撤去する必要がある外構や設備が多い場合は付帯工事費も高くなっていきます。
また、アスベストが使用されている建物や家屋の場合、アスベスト除去にかかる費用も付帯工事費として計上されます。アスベストが使用されていることがわかった場合は、解体工事を行う前にアスベストを除去する必要があります。
県庁・市町村への届出費用
解体工事の主な見積もりの内訳として、県庁・市町村への届出費用も含まれます。主に以下のような項目となります。
- 建設リサイクル法の届出費用
- 諸官庁手続き費用
建設リサイクル法の届出に関しては、解体工事の日程や作業工程の届出を行う必要があります。基本的に解体業者が代行で申請してくれることが多いので、施主が何かをしなければならないというケースは多くありません。
また、解体工事に際しては道路使用許可を得る必要もあります。こちらは道路を管轄する警察署に行って申請を行うことになります。施主が行うケースもありますし、解体業者が代行してくれるケースもあります。
どちらの場合も、一定の費用が発生することは変わりありません。場合によっては解体業者が無償で行ってくれるケースもありますが、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
見積書をよく確認せずに失敗する例
見積書や内訳をよく確認せずに工事を依頼してしまうと、後悔する可能性も高まります。後から何か不都合な点があったとならないように、見積書を確認しなかった場合の失敗例を取り上げていきます。
単純に解体工事の総額費用だけを見て解体業者を選定すると、余計な追加費用がかかるケースも出てきます。優良業者の場合は多くありませんが、悪徳業者の中にはわざと内訳をわかりにくくして、後から追加費用を請求しようとしてくるケースもあります。そうした業者に騙されないように高い意識を持っておくことも大切です。
以下、見積書をよく確認せずに失敗する例。
- 塀や土間の撤去費用が含まれていない
- 庭木やカーポートの撤去費用が含まれていない
- 整地に関する記載がない
- 近隣挨拶の項目がない
- 残置物撤去の有無がない
- 安全対策に関する項目がない etc…
細かい内訳の部分まで記載がない見積書に関しては、あえて解体費用の総額を安く見せている可能性もあります。また、他社と比較して安すぎる総額にも注意が必要です。例えば、カーポートがあることに気付いているにも関わらず、業者があえてその撤去費用を除いて金額提示をしている可能性もあります。
その場合は、契約だけ取って後からカーポートの撤去費用を追加請求することになります。一度契約を結んでしまうと解約するのも手間になるので、それを狙ってあえてわかりにくい見積書を作成することもあります。
施主としてそうした見積書には注意が必要ですし、自らの目できちんと内訳を確認することが求められます。その上で、わからないことや不安に感じる部分があれば、契約を結ぶ前に積極的に質問するようにしましょう。
無駄に追加費用を請求されないようにするためには、その見積もりが「更地にした場合の総額費用」となるのかどうか確認することも大切です。自らの身は自ら守るという意識を持ちつつ、見積書も丁寧に確認することを心がけましょう。
見積書のチェックポイント
地中障害物に関する記載
まず意識しておきたい項目として、地中障害物に関する記載があるかどうかです。図面を見てわかる範囲であれば問題ありませんが、地中障害物に関しては事前の現地調査を行ってもなかなかわからないことが多いです。
浄化槽や古井戸、以前建っていた建物の基礎や廃材など、工事を開始してから地中埋設物があることがわかるケースも少なくありません。その場合は、施主が追加費用を支払うことで地中障害物の撤去作業を行ってもらえます。
ここまでは何の問題もありませんが、見積もり提示の段階で地中埋設物が発見された場合の対応について記載があるかどうか確認することが重要です。主に以下のような流れで追加費用の請求が発生します。
- 地中埋設物の発見
- 施主が地中埋設物を確認(証拠の提示)
- 追加費用の請求と施主の了承
- 追加費用の支払い
- 撤去作業の開始
このような流れで地中埋設物を撤去することになります。見積書にこうした記載がない場合、業者が勝手に地中埋設物を撤去してしまうこともあり、撤去や工事を開始してから高額な追加費用を請求してきます。
こうした施主に不利な条件をなくすために、見積書に地中埋設物が見つかった場合の対応について記載があるかどうか確認することがポイントです。優良業者であれば、きちんと記載してくれることが多いです。万一、記載がない場合はしっかりと質問をして確認するようにしましょう。
室内残置物に関する記載
室内残置物については、施主が処分することが一般的です。冷蔵庫や洗濯機、テレビやエアコンなど、家電製品を中心に自ら撤去することで解体費用の高騰を防ぐことができます。
反対に室内残置物が残っている場合、別途見積もりの対象となり、追加費用請求をされることもあります。この辺も室内残置物が残っている場合の対応について記載があるかどうかを確認しましょう。
場合によっては、室内残置物も解体業者が撤去してくれるケースがあります。その場合の費用感を尋ねておくことで、自らの負担を減らすことができます。施主自ら撤去する場合は、何を残しておいてはいけないのか事前に確認することが重要です。
アスベスト除去費用
アスベスト除去費用に関しても、見積書の提示を受けた段階で確認しておきたいチェックポイントです。アスベストについては、使用されているのかどうか事前にわからないこともあります。その場合は、アスベストが使用されている建物かどうかをチェックした後で解体工事に入っていくことになります。
アスベストが使用されていなければ問題ありませんが、使用されていた場合は除去する必要があります。その際の除去費用に関しても、見積書に記載があるかどうか確認しましょう。
アスベスト除去も使用範囲や量によって費用が大幅に変わっていきます。事前に費用感をある程度想定できなければ、思わぬ高額な出費になってしまうことがあります。そのため、アスベストが使用されていた場合にかかる費用規模や見積もり方法などを提示してもらうようにしてください。
人件費
見積書を確認する際は、解体工事を行う際にかかる人件費にも注意しましょう。解体工事を行う作業員だけでなく、ガードマンやトラックの運転手なども含めて人件費が高くなることが少なくありません。
特に手作業での解体が中心になると、日数や手間もかかりやすくなり人件費がかさんでいきます。ある程度の人件費は仕方ありませんが、他社と比較した場合に高すぎる場合は質問してみるのも良いでしょう。
以下、人件費が高くなりやすいケースについてご紹介します。
- 解体現場が住宅の密集地にある
- 敷地内作業スペースがない(運搬用トラックや重機の搬入ができない)
- 前面道路が狭く、大型トラックが進入できない
いずれも人の手による作業が増えるパターンで、人件費の高騰につながりやすいケースと言えます。立地条件などもあるので、施主だけの力ではどうにもならない部分ですが、上記のようなケースで人件費が高騰しやすいと認識しておきましょう。
産業廃棄物の処分費用
解体工事を行うと、さまざまな形で産業廃棄物が出ることになります。産業廃棄物は廃棄物処理法に則って適切に処分される必要があり、そのための処分費用もかかります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
廃棄物の排出抑制と処理の適正化によって、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的として制定された法律。
産業廃棄物処理費用に関しては、業者によって計算方法もさまざまです。運搬費と処理費用を分けるケースや、トラック1台分の廃棄物量に応じて金額を算出するケースもあります。金額の目安としては、4tダンプ1台あたり(最大積載量目安 2.5㎥強)8万円の処分費用と考えることができます。
産業廃棄物処理費用に関しても、適切に記載があるかどうか確認するようにしましょう。不法投棄などをして、不当に利益を確保しようとする業者もあるので注意が必要です。
家屋構造や立地条件による違い
見積書で総合的に意識しておきたいポイントとしては、家屋構造や立地条件による金額の違いです。同じような家屋や建物であっても、家屋構造や立地条件が異なることは珍しくありません。
その違いが金額の違いになって現れることも多く、施主の負担につながっていきます。解体費用としては、重機やトラックにかかる費用、人件費や廃棄物処分にかかる費用がメインとなります。
その中で、重機やトラックを搬入することができない、人手が多くかかる堅牢な材料と構造で造られているなど、さまざまな条件によって費用規模も変わっていきます。また、人通りが多い場所で作業を行う場合はガードマンを設置する必要があることもあり、費用の高騰につながります。
さまざまな条件が重なって、解体工事にかかる費用が計算されていくことを念頭に置く必要があります。優良業者の場合は、家屋構造や立地条件の違いについて説明した上で最終的な金額提示をしてくれます。そうした業者に依頼することができればベストであり、安心して工事を任せることができるでしょう。
詳細があまりない見積書には要注意
最も危険性が高く注意が必要なのは、詳細があまりない見積書です。「一式○○万円」などと記載がある業者の場合、本当にその費用だけで全ての作業を行ってくれるのか定かではありません。
古くからの伝統や慣習で、詳細を記載せずに見積書を提示してくる業者もありますが、現在の契約書類としては不十分です。特に解体工事は素人ではわかりにくい部分も多く、業者の言いなりになってしまう施主も少なくありません。
コミュニケーションを取る中で、あまり誠意を感じない業者や信憑性に欠ける業者に出会った場合は、契約しないことが重要です。解体業者は1社だけではないので、自分自身が信頼できると思った業者に依頼するのが良いでしょう。
見積もりは複数業者に依頼する
そもそも1社だけに見積もりを依頼すると、提示された金額や工期が適正なのかどうか判断することができません。複数業者に依頼を出すことで、他社との比較の中で適正な金額や工期を判断することができるようになっていきます。
あまりにも高すぎる金額も考えものですが、反対に安すぎる金額提示にも注意が必要です。他社と比較した場合に安すぎる金額を提示してくる解体業者は、違法工事を行っているか不法投棄などを行っている可能性が考えられるからです。
解体工事を行うには一定の費用がかかるのは自然なことであり、その費用を極限まで切り詰めてしまうと、業者側の手元に残る利益がなくなってしまいます。そうなると、必然的に工事の課程や廃棄物処分の課程で経費削減を行わなければなりません。そうすれば、行き着く先は不法工事や不法投棄といった行為になることが多いのが現実です。
こうした業者に工事を依頼すると、まともな解体工事が行われるかどうか定かではありません。場合によっては、施主も被害を被る可能性があるので注意が必要です。
いずれにしても、見積もりを依頼する際は比較対象を持つことが重要なので、複数業者から見積もりを取ることを念頭に置いておきましょう。
解体工事の見積書作成方法
家屋や建物の解体を依頼する場合、解体業者に工事を依頼することが一般的です。その際に、どういった基準や方法で見積もりが作成されているのか疑問に感じることもあるでしょう。
依頼者側としては、見積書を受け取った際の確認事項として把握しておきたい内容のため、解体業者の担当者になったつもりで理解を深めていきましょう。
見積もり作成規定が明確な場合
解体業者によって見積もりの作成方法はさまざまですが、企業や業者として社内的な規定が整っている場合、明確な見積もり作成規定によって計算されます。
規定に沿った計算式を用いて計算を行うことで、どの担当者が見積もりを作成しても同じ水準の金額を提示することができます。見積書には具体的な項目が記載されることが多いですが、その項目ごとに計算式が決められています。
例えば、解体費用であれば「単価×坪数(平米数)」で金額の計算を行います。産業廃棄物運搬費用や処理費用であれば、「単価×重量(体積)」で金額の計算を行います。
その他、養生費用や重機回送費、ガードマン費用や建物調査費用、残置物撤去費用や付帯構造物撤去費用など、独自の算定基準をもとに金額計算を行うことになります。ガードマンであれば「人数×勤務日数」などで計算を行うことができます。
解体業者としての規模が大きい場合は、個別に対応するのではなく、概算を出すという意味で規定を明確にしているケースも少なくありません。
施主としても、ある程度見積もりに関する規定が明確であった方が安心して工事を依頼しやすいというメリットがあります。解体業者としても、金額の計算が簡単であることがメリットとして挙げられます。
見積もり作成規定が不明確な場合
解体業者の中にもさまざまな規模の業者がありますが、規模が小さな業者に関しては担当者の経験や勘に基づいて見積もりを作成することがあります。
特に社長が自らの経験や勘をもとにして、見積もりを作成するケースが多くなっています。規模の小さな業者では、経理担当などの専任担当者がいないケースも少なくありません。そのため、1人の担当者が多くの仕事をこなさなければならず、規定を作らない方が手っ取り早いという考え方をしている業者も多いようです。
見積書の表記としては、「一式○○万円」という形で、項目ごとの具体的な金額は提示されないことが多いです。人件費や産業廃棄物処分費、燃料費やその他の経費などと、会社としての利益を合算して肌感覚で見積もり金額を提示することになります。
もちろん、適当に計算しているわけではなく、これまでの経験を根拠にして見積もりを出しています。施主からすると不安に感じる部分や、不当に高い金額を請求されているのではないかと感じる部分も出てくるでしょう。その辺の不安や疑問点は、複数業者から見積もりを取ることで解消できます。
また、見積もりの作成規定が不明確な場合は、担当者や社長の裁量で金額を決められるため、値引きなどにも柔軟に応じてくれることがあります。他社と比較して高いと感じた場合は、「多少安くすることはできないか」などと価格交渉をしてみることもおすすめです。
項目と単価の表示が基本
解体工事の見積もりについては、項目と単価の表示が一般的であることを理解しておきましょう。
見積もり規定がない場合は「一式○○万円」などと見積もり提示をしてくることもありますが、それは例外的なケースです。
縦書きや横書きの違いはありますが、「解体費用○○万円」「産業廃棄物運搬費用○○万円」「残置物撤去費用○○万円」「養生費用○○万円」など、項目ごとにどれくらいの費用がかかるのか提示するのが基本です。
全ての項目を合算した金額が解体工事における総費用となります。中には建設リサイクル法の提出金額など、記載外にかかってくる費用もあるので、事前に確認しておくことが大切です。
いずれにしても、各項目に対してどのくらいの金額がかかるのかはっきりと確認できることが施主としても大きなメリットです。どの作業にどのくらい費用がかかるのかわからないと、もやもやした気持ちが残ってしまうこともあります。項目ごとに単価の表示がある見積もりであれば、そうした気持ちも払拭することができるでしょう。
詳細まで記載があるケース
項目と単価の表示が基本となる解体工事の見積もりですが、中には詳細まで記載してくれるケースがあります。項目と単価の表示だけでも十分に丁寧ですが、例えば、廃棄物の処理費用と申請費用など、とても細かい部分にいたるまで金額を記載してくれる業者もあります。
ここまで来ると、施主としての納得感も一層高まりやすくなります。詳細まで記載があると細かな部分まで把握できるような形となり、とても透明性の高い見積もりだと言えます。
ガードマンにかかる費用や建設リサイクル法の提出金額など、詳細にわたるまで1つ1つ丁寧に金額を記載してくれます。ここまでやってくれる業者はそれほど多くありませんが、その丁寧さに信頼感も高まっていくことになるでしょう。
書類が丁寧な業者は、その後の解体工事も丁寧に行ってくれるという期待感を抱けます。項目と単価の表示だけでも十分ですが、それ以上やってくれる業者があることも認識しておきましょう。
まとめ
解体工事と見積もりの関係に注目をして、具体的に解説を行ってきました。解体業者に工事を依頼すると、見積もりを提示してもらい、その金額に納得できたら契約を結ぶことになります。見積もりに少しでも不安や疑問がある場合は、その場で解消するべく質問をすることが大切です。
うやむやなまま契約を結んでしまうと、施主にとって不利な条件になる可能性が高まります。不安を覚える業者に対して無理をして工事を依頼する必要はありません。少なくとも2社から3社以上の話を聞き、その中から信頼できる業者に依頼することがおすすめです。見積もり提示の段階から納得した状態で工事を完了してもらえるように、施主としてやるべきことをやっていきましょう。
 解体見積もり広場
解体見積もり広場